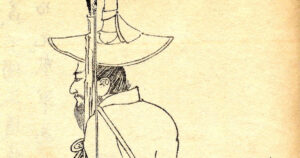語呂合わせ
人を強引(1051)に巻き込む、前九年の役
前九年の役は、源頼義・義家父子が出羽の蝦夷・清原武則と協力し、陸奥の蝦夷・安倍頼時・貞任父子を討伐した戦いです。
前九年の役の様子は、軍記物の陸奥話記に描かれています。
この記事では、前九年の役について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。
目次
蝦夷と俘囚
奈良・平安時代、東北地方(陸奥・出羽)は中央政府の支配が及びにくい地域でした。
この地には「蝦夷」と呼ばれる人々が住み、朝廷に服属した後も「俘囚」として半独立的な自治を保っていました。
俘囚とは、朝廷の支配に属するようになった蝦夷のことをいいます。
その代表が陸奥の豪族・安倍氏でした。
あわせて読みたい
658年 蝦夷・粛慎の征討
語呂合わせ 無言でや(658)り抜く、阿倍の征討 斉明の征討を行いました。 東北経営の始まり 古代日本において、東北地方は「蝦夷の地」と呼ばれ、大和朝廷の直接的な支…
あわせて読みたい
801年 坂上田村麻呂の蝦夷征討
語呂合わせ やれ行(801)け、坂上征討 坂上を降伏させました。 この記事では、坂上田村麻呂の蝦夷征討について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやす…
陸奥の安倍氏
安倍頼時は、俘囚の出身ながら陸奥国で強大な勢力を築きます。
頼時は、朝廷の命令に従わず、事実上の地域支配者となって租税も納めない状態になります。
1051年、国司(受領)が安倍氏を討伐しようとして反撃され、戦争が本格化します。
これが前九年の役の始まりです。
源頼義・義家親子の登場
この事態に対し、朝廷は関東の武士団を率いる源頼義を陸奥守として派遣。
子の源義家も従軍し、親子で東北の戦乱に挑みます。
源頼義
源頼義は、平忠常の乱において、父の源頼信に従って平定したことで武名を挙げていました。
あわせて読みたい
1028年 平忠常の乱
語呂合わせ 人を増や(1028)して、平の乱 平)で起こした反乱です。 追討使に平定されました。 この記事では、平忠常の乱について整理し、高校日本史で問われやすいポ…
安倍頼時から貞任へ
戦いの最中、安倍頼時が戦死し、息子の安倍貞任が抵抗を続けました。
貞任は武勇に優れた人物で、頼義・義家親子との間で激しい戦いが繰り広げられます。
出羽の清原氏の協力
 出羽の清原武則
出羽の清原武則
戦いが長期化する中で、頼義は出羽の豪族・清原武則に協力を要請します。
清原氏は出羽国の俘囚で、陸奥国の安倍氏と対立関係にありました。
清原氏の支援を得た頼義は有利に立ち、戦況が大きく変わっていきます。
安倍氏滅亡
そして、源頼義・義家・清原武則連合軍は、ついに安倍貞任を撃破し、前九年の役は終結します。
これにより、陸奥の豪族・安倍氏は滅亡し、奥州は清原氏が手中に収めることになります。
このことが、源氏にとって遺恨となり、のちの後三年の役につながることになります。