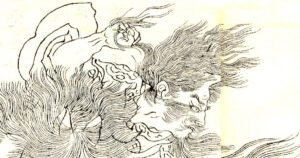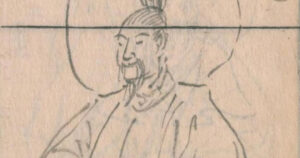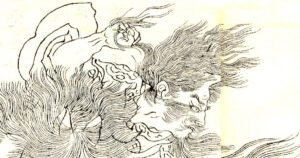長屋王の変は、天皇家の一族である長屋王が、藤原四兄弟によって失脚し、自害に追い込まれた政変のことです。
この記事では、長屋王の変について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。
目次
聖武天皇の治世
 聖武天皇
聖武天皇
聖武天皇は、724年に即位し、奈良時代中期の政治を担いました。
文武天皇の皇子で、母は藤原不比等の娘・宮子です。
聖武天皇は、藤原氏を母にもつ初めての天皇です。
聖武天皇の治世初期、政治権力を握っていたのは皇族の長屋王でした。
一方、聖武天皇の外戚である藤原氏は、自らの影響力拡大を目指していたのです。
長屋王 ― 天武天皇の孫
長屋王は、天武天皇の息子である高市皇子の子、つまり天武天皇の孫にあたります。
左大臣という最高職に就ており、皇族出身の有力な貴族でした。
また、天武天皇系の皇族として、長屋王は皇位継承においても有力な候補と見なされていました。
長屋王の政策
長屋王が行った政策には、百万町歩の開墾計画や三世一身法があります。
あわせて読みたい
722年 百万町歩の開墾計画
語呂合わせ 何使(722)って開墾しよう、百万 百万によって進められた大規模な農地開墾計画のことです。 口分田の不足を補うために計画されました。 口分田とは、朝廷が…
あわせて読みたい
723年 三世一身法
語呂合わせ 難踏み(723)越えて、三世一身法 三世一身法)は、新しく灌漑設備を作って開墾した土地は三世代まで、既存の灌漑設備を利用して開墾した土地は一世代限り保…
藤原四兄弟 ― 藤原鎌足の孫たち
長屋王と対立したのが、藤原不比等の息子たちである藤原四兄弟(藤原四子)です。
彼らは祖父の藤原鎌足から続く藤原氏の権力基盤を固めようとしていました。
南家 ― 藤原武智麻呂
 藤原武智麻呂
藤原武智麻呂
長男の藤原武智麻呂は、南家の祖です。
武智麻呂は長屋王の変において中心的な役割を果たします。
南家の著名な人物としては、藤原仲麻呂(恵美押勝)がいます。
北家 ― 藤原房前
 藤原房前
藤原房前
次男の藤原房前は、北家の祖です。
北家は後に摂関政治を担う藤原氏の本流となる重要な家系です。
北家の著名な人物としては、藤原冬嗣、藤原良房、藤原基経、藤原道長などがいます。
あわせて読みたい
858年 藤原良房、事実上の摂政就任
語呂合わせ やぁ、ご法度(858)、藤原就任 藤原として朝廷の実権を握りました。 摂政とは、幼少の天皇に代わって政務を行う役職のことです。 この記事では、藤原良房の…
あわせて読みたい
884年 藤原基経、事実上の関白就任
語呂合わせ はやし(884)たてられ、藤原就任 藤原として政治を動かすようになりました。 この記事では、藤原基経の事実上の関白就任について整理し、高校日本史で問わ…
あわせて読みたい
1016年 藤原道長の摂政就任
語呂合わせ 祝い群(1016)なす、藤原就任 藤原の地位に就き、藤原氏による摂関政治を最盛期へと導きました。 この記事では、藤原道長について整理し、高校日本史で問わ…
式家 ― 藤原宇合
 藤原宇合
藤原宇合
三男の藤原宇合は、式家の祖です。
717年の遣唐使に参加し、帰国後は軍事や難波宮の造営を担当します。
式家の著名な人物としては、藤原広嗣、藤原百川、藤原種継、藤原薬子などがいます。
あわせて読みたい
740年 藤原広嗣の乱
語呂合わせ 名、知れ(740)る、藤原広嗣の乱 藤原広嗣を排除しようとして起こした反乱です。 この記事では、藤原広嗣の乱について整理し、高校日本史で問われやすいポ…
あわせて読みたい
769年 宇佐八幡宮神託事件
語呂合わせ 南無 宇佐が、宇佐八幡宮の神託を利用して皇位を狙った事件です。 和気が神託を否定し、道鏡の即位を阻止しました。 この記事では、宇佐八幡宮神託事件につ…
あわせて読みたい
784年 長岡京へ遷都
語呂合わせ 納屋 覚え方 784年の長岡京へ遷都は、794年の平安京へ遷都の「10年前」である。 784年 長岡京へ遷都 794年 平安京へ遷都 長岡京天皇によって造営された都城…
あわせて読みたい
810年 薬子の変
語呂合わせ ハート(810)乱れる、薬子の変 薬子兄妹と共に、上皇の復位と平城京の復都を企てた政変です。 太上ともいいます。 現天皇である嵯峨により鎮圧され、薬子は…
京家 ― 藤原麻呂
四男の藤原麻呂は京家の祖です。
京家は他の三家に比べて勢力は劣りましたが、藤原氏の一翼を担いました。
スクロールできます
| 藤原四兄弟 | 特徴 |
|---|
| 藤原武智麻呂 | 長男、南家の祖、長屋王の変を主導 |
| 藤原房前 | 次男、北家の祖、後の摂関政治につながる |
| 藤原宇合 | 三男、式家の祖、遣唐使に参加 |
| 藤原麻呂 | 四男、京家の祖、政治的影響は控えめ |
光明子の立后問題
 光明子(中央)
光明子(中央)
対立の最大の焦点となったのが、光明子の立后問題でした。
聖武天皇の妃の光明子は、藤原不比等の娘で、藤原四兄弟の妹にあたります。
これまで皇后は皇族出身者のみが就任するのが慣例でした。
皇后は、いざという時には天皇に代わって政治をすることもあるため、臣下出身の女性が皇后になることは前例がなく、長屋王はこれに強く反対していました。
長屋王の変 ― 左道を学び国家を傾けんと欲す
藤原四兄弟と長屋王が対立する中で、729年、長屋王に対して「左道を学び国家を傾けんと欲す」という告発がなされました。
「左道」とは呪術を指し、つまり長屋王が「呪術を使って国家を転覆させようとしている」という内容でした。
告発を受けて、朝廷は藤原宇合の指揮する兵で、長屋王の邸宅を軍で包囲しました。
一方的に罪人扱いされた長屋王は、弁明の機会も与えられず、自害に追い込まれました。
これを長屋王の変といいます。
藤原四子政権の確立
長屋王の死後、藤原四兄弟は藤原四子政権を確立しました。
四兄弟がそれぞれ重要な官職に就き、協力して政治を運営する体制です。
この体制により、藤原氏は朝廷政治の中枢を完全に掌握することに成功しました。
光明子、皇后になる
長屋王という最大の反対者を排除した藤原氏は、ついに光明子の立后を実現させました。
光明子は、日本史上初の臣下出身の皇后となりました。
天然痘の大流行
しかし、藤原四兄弟の栄華は長続きしませんでした。
737年、天然痘の大流行が起こり、藤原四兄弟は全員がこの疫病で死亡してしまいました。
天然痘は、新羅から入ってきたと考えられています。
この出来事は当時の人々に大きな衝撃を与え、長屋王の祟りではないかと恐れられました。
藤原氏の権力は一時的に後退することになります。
その後、皇族出身の橘諸兄が台頭することになりました。
あわせて読みたい
740年 藤原広嗣の乱
語呂合わせ 名、知れ(740)る、藤原広嗣の乱 藤原広嗣を排除しようとして起こした反乱です。 この記事では、藤原広嗣の乱について整理し、高校日本史で問われやすいポ…