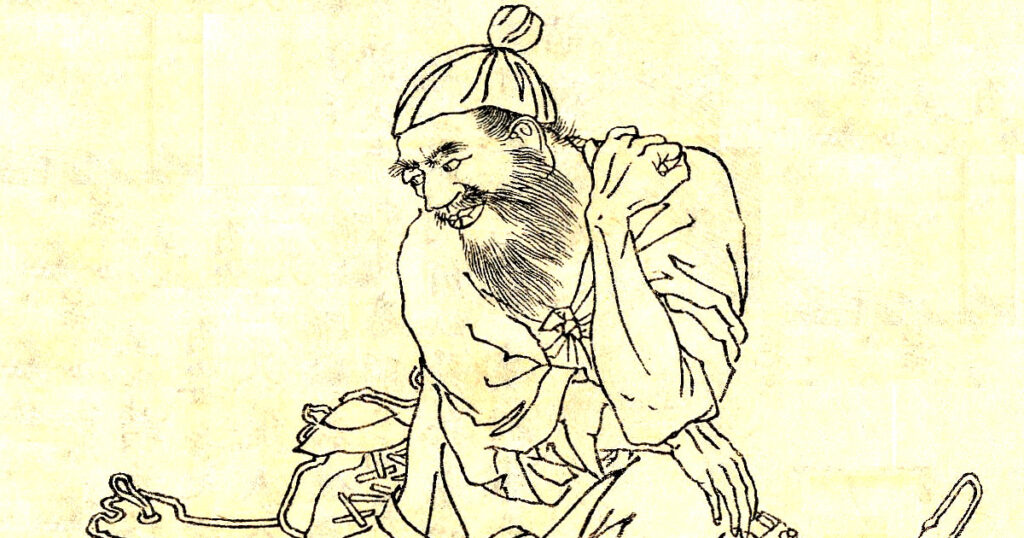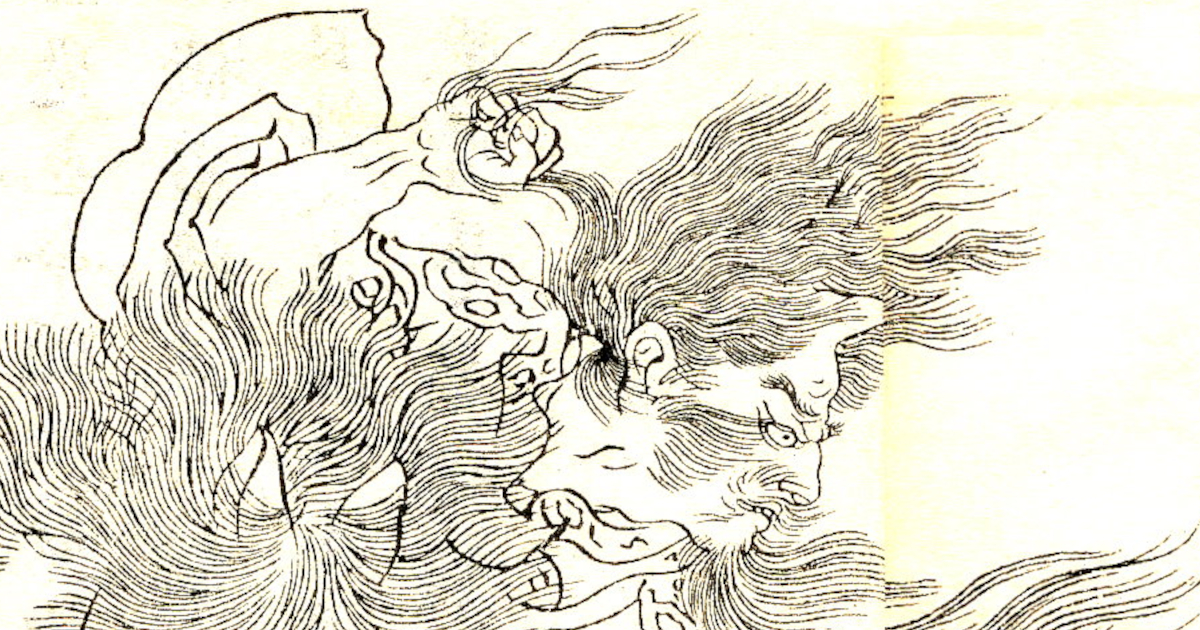語呂合わせ
名、知れ(740)る、藤原広嗣の乱
藤原広嗣の乱は、太宰府に左遷された藤原広嗣が朝廷から吉備真備と玄昉を排除しようとして起こした反乱です。
この記事では、藤原広嗣の乱について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。
目次
橘諸兄が政権を握る
 橘諸兄
橘諸兄
天然痘の流行によって、政治の主導権を握っていた藤原四兄弟が相次いで亡くなると、皇族出身の橘諸兄に主導権が変わりました。
橘諸兄は、藤原氏の勢力を抑えつつ、自らの政治基盤を固めていきました。
重用される吉備真備と玄昉
橘諸兄は、遣唐使から帰国した吉備真備と僧の玄昉を重用し、政治を行いました。
あわせて読みたい
630年 遣唐使の派遣
PHGCOM, anonymous Japanese painter 8-9th century, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 語呂合わせ 無惨 舒明として派遣しました。 この記事では、遣唐使の派遣につ…
吉備真備

吉備真備は、遣唐使として717年に唐に渡り、兵学や史書などの学問を修めて帰国しました。
唐でも知識人として名高く「遣唐使の中で唐で名を上げたのは吉備真備と阿倍仲麻呂の二人のみ」と言われるほどでした。
彼は唐の制度や文化にも精通しており、聖武天皇や橘諸兄から重用されていました。
玄昉
 玄昉
玄昉
玄昉は僧侶として唐に渡り、法相宗を学んで帰国しました。
彼もまた聖武天皇の信任を得て、政治的な発言力を持つようになっていました。
藤原広嗣の乱
吉備真備と玄昉の重用に対して、式家の藤原宇合の子である藤原広嗣が反発しました。
藤原宇合は、藤原不比等の三男です。
藤原広嗣の左遷
しかし、朝廷の政策に異議を唱えたとして、九州の太宰府に左遷させられることになります。
太宰府にいた広嗣は、吉備真備や玄昉を排除する様に訴えましたが、聞き入られませんでした。
広嗣、挙兵する
訴えが聞き入れられなかった広嗣は、反乱を決意し、九州の兵を集めて挙兵しました。
これを藤原広嗣の乱といいます。
大野東人により鎮圧
 大野東人
大野東人
それに対して、朝廷は大野東人を大将軍とする征討軍を派遣しました。
広嗣の軍は朝廷軍と衝突し敗北、捕えられ処刑されました。
遷都を繰り返す聖武天皇
 聖武天皇
聖武天皇
聖武天皇は、乱の影響が平城京に及ぶことを恐れ、740年、山背の恭仁京に遷都しました。
その後、744年には摂津の難波京、近江の紫香楽宮へと都を移していき、不安定な政治状況が続きました。
しかし、結局、745年に平城京へ戻りました。
国分寺建立の詔
なお、聖武天皇は、遷都の最中の741年、藤原広嗣の乱による政治的混乱を仏教の力で鎮めようと国分寺建立の詔を発布しています。
あわせて読みたい
741年 国分寺建立の詔
語呂合わせ 名、良い(741)寺、国分寺建立 国分寺建立を建立するよう命じた詔です。 聖武天皇によって発令されました。 詔とは、天皇の命令のことです。 この記事では…