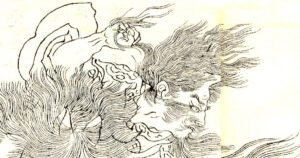覚え方
752年の大仏開眼供養は、552年の仏教伝来(壬申説)から「200年後」です。
東大寺の盧舎那仏(奈良の大仏)が完成し、開眼供養が聖武上皇と孝謙天皇の出席のもと行われました。
この記事では、大仏開眼供養について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。
目次
大仏造立の背景 〜聖武天皇の苦悩〜
 聖武天皇
聖武天皇
奈良時代前半、天然痘の大流行(735~737年)、藤原広嗣の乱(740年)といった社会不安が続きました。
聖武天皇はこうした状況を「仏の力で鎮めよう」と考え、仏教による鎮護国家の実現を目指します。
全国に国分寺・国分尼寺の建立を命じるとともに、その総本山として東大寺に巨大な盧舎那仏の造立を決意したのです。
盧舎那仏とは、宇宙の真理を体現する「毘盧遮那仏(大日如来)」のことです。
あわせて読みたい
740年 藤原広嗣の乱
語呂合わせ 名、知れ(740)る、藤原広嗣の乱 藤原広嗣を排除しようとして起こした反乱です。 この記事では、藤原広嗣の乱について整理し、高校日本史で問われやすいポ…
あわせて読みたい
741年 国分寺建立の詔
語呂合わせ 名、良い(741)寺、国分寺建立 国分寺建立を建立するよう命じた詔です。 聖武天皇によって発令されました。 詔とは、天皇の命令のことです。 この記事では…
大仏建立の詔(743年)
743年、聖武天皇は大仏造立の詔を発布し、盧舎那仏の造立を宣言しました。
大仏の造立地は当初、紫香楽宮(現在の滋賀県)が予定されていましたが、山火事や地震などの災害が相次いだため、最終的に平城京の東大寺に決定されました。
行基の尽力
聖武天皇は、大仏建立を発願したものの、膨大な資金と労働力が必要でした。
そんな中、僧侶の行基は各地を巡り、大仏造立の意義を説き、民衆から資金や労働力を集めました。
これらの功績により、745年、行基は大僧正に任命されます。
これは日本初の大僧正でした。
大僧正とは、朝廷の定める僧侶の位の最高位です。
しかし、開眼供養の直前に亡くなったため、儀式には参加できませんでした。
開眼供養(752年)
 孝謙天皇
孝謙天皇
聖武天皇の退位後、孝謙天皇の治世下の752年に大仏が完成し、大仏開眼供養が行われました。
開眼供養とは、仏像に眼を書き入れて魂を宿らせる儀式のことです。
聖武上皇や娘の孝謙天皇のもと盛大に行われ、参列者は約1万人を超え、海外からも使節が参加しました。
鎮護国家と大仏の意義
聖武天皇が目指したのは、仏教の力によって国家を安定させる「鎮護国家」思想の実現でした。
その象徴として建てられた盧舎那大仏と東大寺は、仏教と政治の結びつきを如実に表すものであり、奈良仏教の中心として後世に大きな影響を与えました。
なお、752年の大仏開眼供養の翌年、753年には鑑真が来日し律宗を伝えることになります。
あわせて読みたい
753年 鑑真の来日
語呂合わせ 難が来日 唐の僧である鑑真を伝えました。 この記事では、鑑真の来日について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。 鑑真来…
理解を深めるQ&A
よくある質問を通して、学びをさらに深めよう!
大仏造立の詔と同じ743年に発令された土地制度は何?
墾田永年私財法です。
あわせて読みたい
743年 墾田永年私財法
語呂合わせ 無しさ(743)期限は、墾田永年私財法 墾田永年私財法)は、開墾した土地の永久私有を認める制度です。 聖武天皇の時代に橘政権のもとで発布されました。 こ…